そういう意味で、今回の課題図書のサブタイトル「人がつながるしくみをつくる」は、とても親和性が高いかなとか。
つい先日福岡にいらっしゃったにも関わらず、残念ながら講演を聴きそびれてしまった山崎亮さん。改めて本から触れていきます。
__________________
1.風景を創るということ
著者である山崎氏がいわゆる通常のランドスケープデザインから、コミュニティデザインへと少しずつ舵を切ったのは、つまり「ハード」から「ソフト」への移行であった。
「つくる」ことをいったん辞め、デザインの行き先を多くの人の手に委ねる。また委ねると言っても投げっぱなしにせず、「つくるしくみをつくる」ことが彼の仕事だという。
形としての公園が完成したら終わりではなく、市民参加型の「パークマネジメント」という概念を導入したプロジェクトでは、NPO等の市民活動団体をディズニーランドのキャストになぞらえて運営に参加させた。
それはいわゆる「ボランティア」のイメージではなく、楽しんでいる人がいる場所に、更に人が集まってくるというごく自然な営み。
ここで重要なのはきっと「余白があること」だ。
最初から100%完成したものが目の前にあれば、人は消費者となってしまう。山崎氏がデザインした(あるいは、しなかった)場の「ホワイトスペース」にこそ、人が当事者として場に関わっていくこと、そしてコミュティが作られていく理由があるのだと思う。
------------------
2.人を巻き込むしかけ
その後「まちづくり」の請け負い人(ファシリテーター)として全国各地でプロジェクトを進める山崎氏の仕事は、必ず共通して同じ地点からスタートしている。それは、「ヒアリング」。
まち を つくる と言っても、外から人が入って来て、建物を作ったりイベントを打って、一時的に観光客を増やしたり、外からの流れるお金を増やすような文脈の「町興し」とは全く逆のアプローチだ。
その土地に住む、これからもその町に生き未来に責任を負う人々の声を聴く事から始める。対話はこちらが話し始める事からはスタートしない。
昔ながらのムラコミュニティには、古くから続く対立構造や権力関係、また、触れてはいけないタブーも少なくはない。そこから切り込んでいく手段として、彼の用いる手法に二つ興味深いポイントがある。
1つ目…しがらみにとらわれず、かつ素直で純粋な心を持って大人達に接することが出来る部外者「学生」の力を借りる
2つ目…その土地の対立構造の前線ではなく、後ろにいる人々に焦点をあて、そこから仲良くなっていく。ex)地域の「お母さん達」「子ども達」
特に2つ目については、立場や責任を重んじる日本社会において、良い意味で有益な「根回し」であると考えられるし、また、彼が作ったコミュニティでは、その後の維持管理の為にファシリテーター役のスタッフや組織を間に挟んでいることからも、人間関係のアングルづくり・潤滑油に、非常に丁寧な思いを払っていることがわかる。
------------------
3.みんなができること
島根県海士町は、通常、外部のシンクタンクに任せっきりになりがちで実を得ることが少ない「総合振興計画」を住民参画で制作した。
そこに関わった山崎氏が伝えたメッセージは
「1人でできること、10人でできること、100人でできること、1000人でできること。」というもの。
グループワークショップで発案されたプロジェクトをの後に「1人出来ることは明日からでも始める、10人で出来ることはそのままグループのチームで取りかかる、100人、1000人必要なものは行政と恊働していこう」となった。
それは、逆に言えば何でも行政任せにしないということ、私/共/公のラインを探っていくことで、「新しい公共」の担い手としての自覚を目指したとも言える。
更に、最終的にまとめられた海士町総合振興計画の別冊「海士町をつくる24の提案」では、海士町の祭りの象徴であるしゃもじのキャラクターに、それぞれのプロジェクトの発案者を似せた顔を掲載することで、「実行しなきゃまずいなあ」「参加しなかった友人にも見せたい」との声があがり、両面で動線設計が見事にデザインされたものとなった。
デザインとは、何だろうか。
少しでもかじったことがある人なら、一般的には「そのものを綺麗に見せるためのお化粧」であると誤解されていることが多いように感じるのではないか。
311東日本大震災で、山崎氏のstudio-Lと博報堂がコラボレーションして、学生コンペ等を通して生まれた「できますゼッケン」などは、課題解決そのものに至るツールではなく、人々がかかわり合う事での課題解決力を高める為の触媒になる、プロセスデザインであったと言えるだろう。
デザインの可能性(本書より転載)
1)継続を促すデザイン
2)決断を支えるデザイン
3)道を標すデザイン
4)溝を埋めるデザイン
5)関係を紡ぐデザイン
------------------
最後に、山崎氏の関わるプロジェクトは長期に渡るものが多い、長いものであれば10年弱の道のりのまだ半分にも至っていないというものすらある。
一時的ではなく、長く続いていく価値を作る為には、ゆっくり進むことが大事。人が変化のスピードについてこれるように と言う。
しかし、その目指す先に対してだけではなく、きっとその道のりがゆるやかに、しかし一歩一歩未来に近づいていくようなものであればこそ、多くの人が合流することができるのだろう。
結果としてのアウトプット、プロダクト、成果ばかりを見続けることが当たり前になってしまった僕たちの社会が、もう一度その歩む道(プロセス)の豊かさに気付けた時、僕たちは「生きる」ことそのものを目的として生きることが出来るのかもしれないと思った。
__________________
もっと深く学びたい、読んでみたいという方はぜひお買い求めください。
学芸出版社 山崎亮さんインタビュー http://p.tl/Fn2L
このチャレンジに共感した!役にたった!応援する!と言う方はぜひ
JustGivingからご寄付をお願いします* → http://p.tl/L-o9
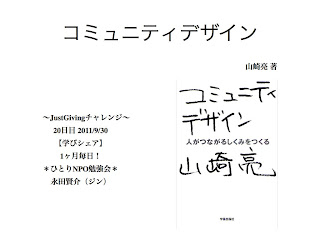



0 件のコメント:
コメントを投稿